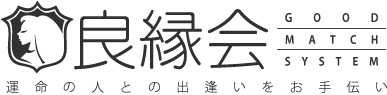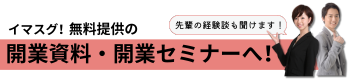結婚相談所を始めるのに、何か資格を取らければいけないの?どんな資格が必要なの?結婚相談所を始めたいと思っているから知りたい。
そんな疑問にお答えします。
この記事を読むと
・結婚相談所を始めるのに必要な資格が分かる。
・事業者として守らないといけない法律が分かる。
・どんな人が仲人に向いているのか分かる。
●記事の信頼性●
結婚相談所の連盟を20年運営しています。
先にネタバレしてしまうと、結婚相談所を開業するのに特に資格は必要ありません。「やりたい!」と思ったら誰でも簡単にはじめられてしまいます。
しかし運営が自由に出来る訳ではありません。結婚相談所が守るべき法律があります。
結婚相談所運営に関連する法律・名称
- 特定商取引法
- クーリングオフ
- 中途解約
- 個人情報保護法
聞いたことがある名称もあると思いますが、どんな法律なのかまでは知らない方も多いのではないでしょうか。そこで、特定商取引法やクーリングオフについて詳しく説明したいと思います。
今後の結婚相談所運営にお役立て下さい。
1.特定商取引法とは
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法ガイド
結婚相談所は結婚情報サービスとして特定商取引法の特定継続的役務提供に含まれます。
契約期間が2ヶ月以上、且つ入会金(含む月会費)5万円超の契約を行う業者は、特定継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。
●クーリングオフの説明
●中途解約時返戻金の計算方法の説明
●資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応
なんだか難しい言葉が並んでますが、簡潔に説明すると結婚相談所は該当するというこです。
2.特定継続的役務提供とは
難しい名称までは覚える必要はありません。こんな言葉がある程度に覚えておけば大丈夫でしょう。
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
3.結婚相談所が特定商取引方について、知っておく3つのポイント!
●勧誘の禁止事項
1.誇大広告の禁止
商品の内容・価格などが実際より優れているように表現し、消費者に誤認を与える広告
2.不実告知による勧誘の禁止
事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。消費者契約法では、不実告知により消費者に誤認が生じた場合、消費者は当該契約を取り消すことができるとされる。「便利である」など主観に基づく表現は不実告知には当たらない。
3.威迫・困惑による勧誘の禁止
「威迫」とは、脅迫に至らない程度の、人を不安にさせるような行為をいいます。
「困惑」とは、困り戸惑わせることをいいます。
●契約上の制限
1.クーリングオフが可能
2.中途解約が可能
3.中途解約時の損害賠償額の制限
●事業者の義務 契約時、契約前の書類の交付
結婚相談所は契約にあたり上記2つの書類を渡さなければいけません。
1.概要書面:契約前に交付して重要事項を確認してもらう。
消費者が契約を締結する前に、その判断材料として知っておくべき情報を提供する書面
2.契約締結時書面(契約書):契約の締結を行ったその場で交付することとなります。
4.契約上の制限について
4-1.クリーングオフが可能
クーリングオフとは
契約から一定期間であれば、理由を問わず、一方的に契約の解除ができる制度。
クーリングオフの期間は、契約した日より 8日間です。またクーリングオフ期間(8日間)を過ぎても、理由を問わず、会員は中途解約ができます。
簡単に説明すると、契約した後、頭を冷やして(クーリングオフ)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
無条件の解約となりますので、結婚相談所は全額返金しなければいけません。
4-2.中途解約が可能
結婚相談所への入会後に消費者が契約を途中で解約すること。消費者は1年契約で入会するパターンが多く、クーリングオフ期間が過ぎても途中で止めたくなったらいつでも止めることができるのが中途解約です。
中途解約の理由は一切不要であり、解約の際に結婚相談所に支払わなければならない解約料も法律で上限が定められています。
「うちの相談所は入会後の返金もありませし、途中で解約も出来ません!」このようなことは法律で認められていませんので注意が必要です。
但し全額返金する必要はなく、サービス提供前と提供後では損害賠償額が異なります。
●結婚相手紹介サービスの場合中途解約時の損害賠償額の上限
サービス利用前:3万円
サービス利用後:未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額
【サービス提供前の例】プロフィールも作成していない、お見合いシステムにも登録していない状態
1年契約
入会金50,000円+活動サポート費60,000円=入会時に必要費用の合計:110,000円
110,000円-30,000円(中途解約時、上限費用)=80,000円が返金額
【サービス提供後の例】結婚相談所で3ヶ月活動後、中途解約
1年契約
入会金60,000円+活動サポート費60,000円=入会時に必要費用の合計:120,000円
すでに受けたサービス料:入会金50,000円と活動サポート3ヶ月分(月割り:5,000円)=65,000円は返金しなくても大丈夫です。
残りの活動サポート費9ヶ月分(45,000円)が返金対象となります。
しかし全額返金する必要はなく未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額は、損害賠償額として請求することが出来ます。
45,000円×2割=9,000円
20,000円より9,000円の方が低い額となるので9,000円が適用されます。
45,000円-9,000円=36,000円が返金額となります。
返金時の注意点
月会費として1年分先払いで支払ってもらう場合、中途解約時返金の対象になりません。あくまでも月会費となるので、活動していない月の費用は全額返金となります。
5.個人情報の取り扱いも注意!
個人情報とは
『個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。』
勘違いしやすいのが名前や住所だけではなく、個人を特定できるものは全て個人情報になるということです。結婚相談所ならプロフィール写真だけでも個人を特定できるものになります。
結婚相談所の規模はどうあれ、個人情報の取り扱うことを意識しなければいけません。
個人情報の5つ注意点
- 「お見合い相手、結婚相手を探す際に利用する」など、利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません。
- 結婚相談所に入会する際、様々な書類の提出義務があります。預かった書類は管理体制が大切になります。
- お相手の結婚相談所から離婚理由などを聞かれた場合、本人に確認しないで勝手に伝えてしまうのはNGです。お見合いで本人に直接聞くのはOKです。
- 退会後は速やかにシステムより情報を削除する。
- マイナンバーは預からない
6.結婚相談所を始めるためのステップと成功事例
6-1.結婚相談所の業界動向と市場分析
結婚相談所業界は、少子高齢化や晩婚化、そして社会的孤立の増加といった背景から、需要がますます高まっています。
2020年の市場規模は約600億円とされ、年々成長しています。
特に都市部では、忙しいビジネスパーソンをターゲットにしたサービスが好評です。
また、オンラインサービスの拡大により、地方在住者や忙しい現役世代も利用しやすくなっています。
競合他社の分析においては、サービスの質やサポート体制、成婚率の高さが成功の鍵とされています。
具体的な競合分析として、大手と中小規模の結婚相談所の強みや弱みを比較し、それぞれの市場での立ち位置を明確にすることが重要です。
6-2.資格が不要な理由と必要なスキル
結婚相談所を開業するためには特別な資格は必要ありません。しかし、成功するためには以下のスキルや知識が求められます。
コミュニケーション能力: クライアントとの信頼関係を築くために必須です。
カウンセリングスキル: クライアントの悩みや希望を聞き出し、適切なアドバイスを提供する能力。
マーケティング知識: 効果的な宣伝や集客方法を理解し、実践する力。
成功事例の紹介
具体的な成功事例として、A相談所では独自のマッチングノウハウを開発し、成婚率を50%以上に引き上げることに成功しました。
彼らは、顧客のライフスタイルや価値観を重視したマッチングを行うことで、理想的なパートナーとの出会いを実現しています。
成功の要因としては、顧客一人ひとりにカスタマイズされたサービスを提供し、専任のカウンセラーがきめ細やかなサポートを行うことが挙げられます。
6-3.無料で学べる情報源・勉強方法
結婚相談所を開業するにあたり、最も不安を感じやすいのが「どこで何を学べばいいのか分からない」という点です。
特に起業初心者や異業種からの参入者にとって、法律・集客・心理学・カウンセリングなど学ぶべき領域は広範囲にわたります。
しかし、すべてをお金を払って学ぶ必要はありません。現代は「無料で学べる有益な情報」が豊富に存在しています。
ここでは、実践者がよく活用している無料学習法と、おすすめの勉強ステップをご紹介します。
① 公的機関の創業支援を活用する
-
中小企業庁・商工会議所・地方自治体の創業支援講座
これらの団体は、創業希望者向けに「起業の基礎知識」「ビジネスモデル構築」「法的手続きの流れ」などの無料セミナーやeラーニングを提供しています。
特に、創業時に助成金・補助金を考えている方には、こうした講座への参加が要件になっていることもあるため、早めに確認しておくと良いでしょう。 -
消費者庁や総務省の法令ガイド
特定商取引法や個人情報保護法に関する「正しい情報」を一次情報として得ることができます。公式サイトからPDF資料もダウンロード可能です。
② YouTube・ポッドキャストで“ながら学習”
-
起業家・カウンセラー・結婚相談所運営者の発信
YouTubeでは、「実際に結婚相談所を起業した人の1日」や「成婚率を上げるカウンセリング方法」など、実務に即した内容が豊富にあります。
-
音声メディア(Voicy、Spotifyなど)
移動中や家事の合間にも耳で学べるため、隙間時間を有効活用できます。心理学・営業術・マネジメントに関する番組が特におすすめです。
③ SNS・note・ブログで“生の声”を集める
-
X(旧Twitter)やInstagramで現役の相談所をフォロー
日々の集客や失敗談、問い合わせ対応、会員対応の工夫などがリアルに発信されています。「他人の実例から学ぶ」のは非常に有効な方法です。
-
noteやブログで運営の裏側を学ぶ
たとえば「地方で結婚相談所を黒字化させた話」など、実体験ベースの記事は非常に参考になります。無料で読める投稿も多く、有料記事よりもリアルな情報が多い傾向があります。
④ 書籍+ネット検索の“ハイブリッド勉強法”
-
図書館やKindle Unlimitedでビジネス書を読む
結婚相談所に特化していなくても、「マーケティング」「ブランディング」「カウンセリング」「起業の基本」などは汎用性が高く、多くの書籍で学べます。
-
読んだ内容をすぐ検索で深掘り
本で得た知識を「今の時代ならどう応用できるか?」と検索・検証することで、自分の運営方針に落とし込む力が付きます。
学んだ内容は必ず「アウトプット」する
無料で学んだことは、“聞いただけで満足”にならないようアウトプットすることが大切です。
たとえば、以下のような形で実践してみましょう:
- ブログやSNSで学んだ内容を発信してみる
- 自分用の「運営マニュアル」をまとめて整理する
- 家族や知人に説明してみる(“人に話す”ことで理解が深まります)
- これから開業を目指す仲間と情報交換してみる
アウトプットには知識の定着だけでなく、自信を持ってお客様に説明する練習にもなります。特に法律やサービス内容などの難しい部分は、アウトプットを通じて自分の言葉で話せるようになることが大切です。
また、発信を続けることで自然とあなた自身のブランディングにもつながっていきます。
6-3.個人の結婚相談所だからこそ顧客レビューも意識する
顧客の声やレビューは信頼性を高めるための重要な要素です。
例えば、東京の相談所を利用したAさんは、「カウンセラーの丁寧な対応と親身なアドバイスが大変心強かった」と語っています。
Bさんは、「マッチング精度が高く、理想の相手と出会えた」と高評価をしています。
これらのポジティブなレビューは、ウェブサイトやパンフレットに掲載することで、新規顧客の信頼を得ることができます。
また、顧客満足度調査を定期的に実施し、その結果を公表することで、透明性を持った運営をアピールすることも効果的です。
6-4.最新のトレンドや技術も取り入れる
最新のトレンドとして、オンラインカウンセリングやAIを活用したマッチングシステムが注目されています。
リモートワークの普及に伴い、オンラインでの相談や面談のニーズが急増しており、これに対応するためのプラットフォームが整備されています。
オンラインでの面談は相談所にとってもメリットが多く、移動や準備などの時間のロスを減らしてくれます。
空いた時間でSNSの投稿やプライベートに時間を使うことも可能になります。
AI技術を用いたマッチングシステムでは、顧客の細かいプロフィールデータを分析し、より精度の高いパートナーを紹介することが可能です。
これにより、従来のマッチングよりも高い成婚率が期待されます。
7. 開業後によくある失敗例とその回避法
結婚相談所を無事に開業しても、運営を続けていく中で「思うようにいかない」「集客できない」と悩むケースは少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンと、その回避策を具体的に解説します。
【失敗例①】「集客できない」
理由:SNSやHPでの情報発信が不十分だったり、そもそもターゲット層に響くコンセプトが設定されていないことが原因です。
回避策:
- 開業前からInstagramやX(旧Twitter)で情報発信をスタートする
- 「どんな人に、どんなサポートができるか」を具体的に打ち出す
- 地域や年齢層に特化することで、見込み客に刺さりやすくなる
【失敗例②】「会員が増えない・定着しない」
理由:初回カウンセリングの質が低かったり、入会後のフォローが薄い場合、信頼関係が築けず退会につながることがあります。
回避策:
- 最初の面談で「この人なら任せたい」と思ってもらえるヒアリング力を磨く
- 活動開始後もLINEや面談でこまめにフォローし、“見守られている安心感”を提供する
- 会員1人ひとりに合わせたサポート内容を記録し、定期的に見直す
【失敗例③】「法令違反によるトラブル」
理由:契約時にクーリングオフや中途解約の説明を怠る、契約書が不備だったなどで、トラブルになるケースが実際にあります。
回避策:
- 特定商取引法と個人情報保護法の要点を自分の言葉で説明できるようにしておく
- 契約書や概要書面は法令に準拠したテンプレートを使用し、アップデートも定期的に行う
- 開業前に法律セミナーや連盟の勉強会に参加し、知識を補強しておく
【失敗例④】「価格設定が曖昧・競合とかけ離れている」
理由:他相談所よりも極端に安くしてしまい利益が出ない、高すぎて選ばれないというケース。
回避策:
- 地域の競合調査をしたうえで、「価格 × サービス内容」のバランスを見直す
- 料金に見合うサポートがあることを、SNSや説明時に明確に伝える
- 成婚料やお見合い料なども含めて、わかりやすい料金体系を作る
結婚相談所を始めるのに資格は必要か?のまとめ
結婚相談所をはじめるのに特に資格は必要ありません。しかし事業者として覚えなければいけない法律はあります。特定商取引法などの契約に関する法律関連を守るのはもちろん、個人情報を取り扱っていることを自覚しておく必要があります。
個人情報の取り扱いや特定商取引法など、ルールを守って健全な結婚相談所運営を心掛けて下さい。